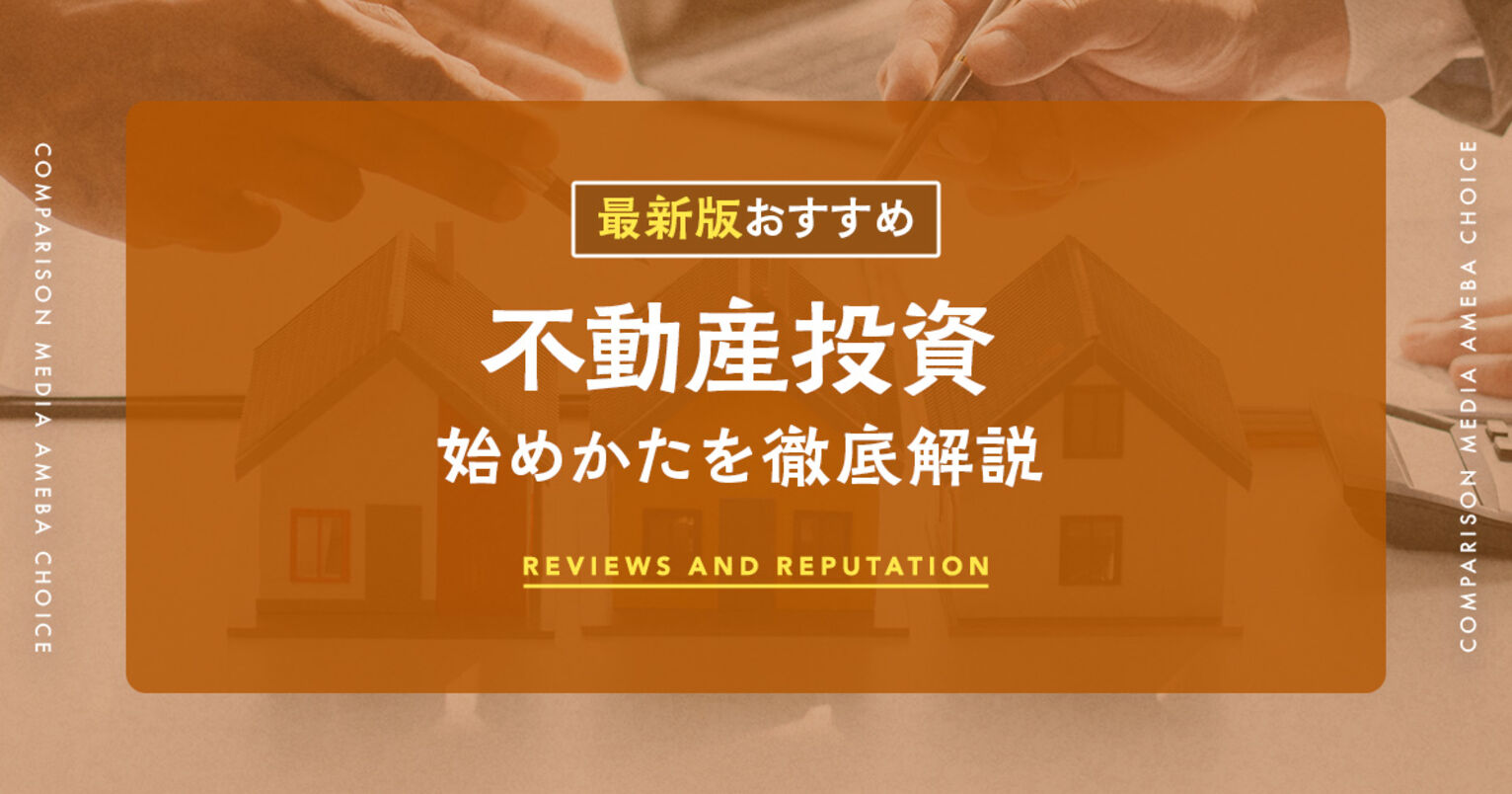
将来のために不動産投資をおすすめされても、初心者には不安がつきもの。失敗例を見ると、どの会社を選べばいいか迷いますよね。
この記事では、ランキング形式でおすすめの不動産投資会社を紹介します。
メリットだけでなく、融資の金利や節税効果、利回りについても解説。公務員の方や、まずは本で学びたい方も必見です。この記事を読めば、あなたにぴったりのパートナーが見つかります。
- 不動産投資会社のおすすめ人気ランキング12選
- 不動産投資会社の選びの7つのポイント
- 1. 会社の信頼性と安定性
- 2. 得意な物件種別・エリア
- 3. 管理戸数と95%以上の入居率
- 4. 手数料体系の透明性
- 5. メリット・リスクの両方を説明する担当者か
- 6. 購入後まで続くサポート体制
- 7. 提携金融機関の豊富さ
- 【要注意】避けるべき不動産投資会社の特徴
- そもそも不動産投資とは?メリット・デメリットを解説
- 不動産投資の7つのメリット
- 少額の自己資金で大きな資産を築ける(レバレッジ効果)
- 長期にわたり安定した家賃収入(インカムゲイン)が期待できる
- 相続税対策になる
- 所得税・住民税の節税につながる場合がある
- 団体信用生命保険で生命保険の代わりになる
- インフレに強い現物資産である
- 売却して利益(キャピタルゲイン)を狙うことも可能
- 不動産投資のデメリット(リスク)と対策
- 空室リスク
- 家賃滞納リスク
- 老朽化・修繕リスク
- 価格変動・売却損リスク
- 金利上昇リスク
- 流動性の低さ(すぐに現金化できないリスク)
- 災害リスク
- 事故リスク
- 【5ステップで解説】不動産投資の始め方
- STEP1|自己資金計画・リスク許容度の棚卸し
- STEP2|不動産投資会社に相談・面談
- STEP3|物件の提案・検討
- STEP4|不動産売買契約・ローン契約
- STEP5|物件の引き渡し・賃貸管理開始
- 不動産投資の費用は?自己資金はいくら必要?
- 不動産投資に必要な自己資金の目安は物件価格の1〜2割
- 自己資金以外にかかる諸費用の内訳
- 【出口戦略を考えよう】不動産投資の3つのゴール
- 不動産投資に関するよくある質問
- 初心者がまず読むべき必読書3選
- まとめ
不動産投資会社のおすすめ人気ランキング12選
「どの会社を信じればいい?」「大切な資産を預けるのに失敗したくない」パートナー選びは、不動産投資における最も重要で、最も難しい第一歩です。
そこで本記事では、その重要な会社選びで迷わないために、「実績」「運用力」「信頼性」という客観的なデータに基づいて優良企業12社を徹底比較。ランキング形式でご紹介します。
- 管理戸数(実績・規模):35点
- 入居率(運用力):35点
- 上場市場(信頼性):25点
- 対応エリア(将来性):2点
- 主な物件種別(専門性):3点
| 順位 | 不動産投資会社名 | 管理戸数 | 入居率 | 上場市場 | 主な物件種別 | 対応エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 |  FJネクスト FJネクスト | 24,542件 (2025年2月時点) | 99% | 東証プライム (親会社: 株式会社FJネクストホールディングス) | 分譲マンション、区分マンション | 首都圏 (東京、神奈川) |
| 2位 |  RENOSY RENOSY | 32,452戸 (2024年10月末時点) | 99.6% (2023年4月時点) | 東証グロース | 新築・中古マンション、新築・中古アパート、戸建て | 東京23区、川崎、横浜、大阪、神戸、京都、福岡、海外 |
| 3位 |  シノケンハーモニー シノケンハーモニー | 50,000戸以上 | 98.75% (2024年年間平均) | 東証スタンダード (親会社: 株式会社シノケングループ) | 区分マンション | 首都圏、都心部 |
| 4位 |  プロパティエージェント プロパティエージェント | 5,840戸 | 99.93% | 東証プライム (親会社: ミガロホールディングス株式会社) | 区分マンション | 東京、横浜 |
| 5位 |  プレサンスコーポレーション プレサンスコーポレーション | 25,000戸以上 | 99% | 東証スタンダード | 新築マンション、中古マンション | 近畿圏、東海圏、首都圏、沖縄 |
| 6位 |  グローバル・リンク・マネジメント グローバル・リンク・マネジメント | 約2,000戸 | 99.21% (2024年年間平均) | 東証プライム | 一棟アパート・一棟マンション、区分マンション | 東京都心 |
| 7位 |  トーシンパートナーズ トーシンパートナーズ | 295棟14,500戸以上 (2025年2月時点) | 99%以上 | 非上場 | 区分マンション | 首都圏 |
| 8位 |  J.P.Returns J.P.Returns | 5,657件 (2025年3月末時点) | 99.96% (2025年3月末時点) | 非上場 | 中古区分マンション | 東京都心部、横浜、川崎 |
| 9位 | 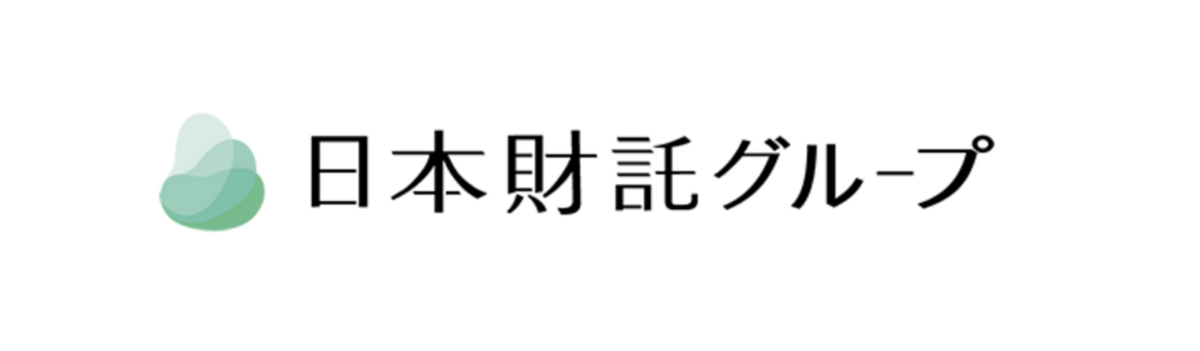 日本財託 日本財託 | 10,808戸 (居住用) | 98.37% | 非上場 | 中古ワンルームマンション | 東京、神奈川 |
| 10位 |  エイマックス エイマックス | 1,836戸 | 99.1%(2023年7月時点) | 非上場 | 中古区分マンション、中古一棟 | 東京23区、横浜 |
| 10位 |  インヴァランス インヴァランス | 4,800戸以上 | 98.84% (2023年4月末時点) | 非上場 (親会社: 大東建託株式会社, 東証プライム) | 区分マンション | 東京23区、神奈川 |
| 12位 |  REISM REISM | 2,653戸 | 97.29% | 非上場 | 中古マンション (リノベーション) | 東京23区 |
不動産投資会社の選びの7つのポイント
ここでは、会社選びで失敗しないための7つの重要なポイントを解説します。これらの基準をもとに、複数の会社を比較検討してみましょう。
1. 会社の信頼性と安定性
まず確認すべきは、会社の信頼性と安定性です。不動産投資は、購入後何十年にもわたる長い付き合いになります。
会社の設立年数や資本金、事業実績などを確認し、安定した経営基盤があるかを見極めましょう。
会社のウェブサイトやパンフレットだけでなく、第三者の口コミや評判も参考にすると、より客観的な判断ができます。過去に行政処分を受けていないかも、信頼性を測るうえで重要なチェックポイントです。
2. 得意な物件種別・エリア
不動産投資会社には、それぞれ得意とする物件の種別やエリアがあります。
例えば、都心の新築ワンルームマンションに強い会社、地方の中古一棟アパートを専門とする会社など、その特徴はさまざまです。
安定した家賃収入を重視するなら都心部、高い利回りを狙うなら地方都市など、自分の目的に合った会社を選びましょう。
3. 管理戸数と95%以上の入居率
購入後の賃貸管理は、不動産投資の安定性を左右する重要な要素です。その会社の管理能力を測る指標となるのが、「管理戸数」と「入居率」。
管理戸数が多ければ、それだけ多くのオーナーから信頼されている証拠であり、経験やノウハウが豊富であると判断できます。
また、入居率がコンスタントに95%以上を維持している会社は、空室リスクを抑えるための優れた管理体制を持っていると言えるでしょう。
4. 手数料体系の透明性
不動産投資には、物件価格以外にもさまざまな手数料がかかります。仲介手数料や管理委託料、サブリース(家賃保証)の手数料など、何にどれくらいの費用がかかるのか、事前に明確に提示してくれる会社を選びましょう。
手数料体系が不透明だったり、質問に対して曖昧な回答しかしない会社は要注意です。契約前にすべての費用について書面で説明を受け、納得できるまで確認することが大切です。
5. メリット・リスクの両方を説明する担当者か
不動産投資には、家賃収入や節税といったメリットがある一方で、空室や金利上昇などのリスクも存在します。
信頼できる担当者は、メリットばかりを強調するのではなく、潜在的なリスクについても包み隠さず説明してくれます。
「この物件なら安心です」といった甘い言葉だけでなく、具体的なリスクとその対策をセットで提案してくれる担当者こそ、あなたの良きパートナーとなるでしょう。
6. 購入後まで続くサポート体制
不動産投資は、物件を購入したら終わりではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。
入居者募集から家賃の集金、クレーム対応、退去時の手続き、そして毎年の確定申告まで、さまざまな業務が発生します。
特に本業で忙しいサラリーマンや公務員の方にとっては、これらの業務を代行してくれる手厚いサポート体制が不可欠です。どこまでサポートしてくれるのか、その範囲と費用を事前に確認しておきましょう。
7. 提携金融機関の豊富さ
不動産投資の多くは、金融機関からの融資(ローン)を利用して行います。提携している金融機関が多ければ多いほど、投資家一人ひとりの状況に合わせて、より有利な金利や条件のローンを提案してもらえる可能性が高まります。
低金利で融資を受けられれば、毎月のキャッシュフローが改善し、投資の成功確率も上がります。会社の提携金融機関の数や種類も、重要なチェックポイントのひとつです。
【要注意】避けるべき不動産投資会社の特徴
優良な不動産投資会社がある一方で、残念ながら投資家の利益よりも自社の利益を優先する会社も存在します。
以下に挙げるような兆候が見られた場合は、一度立ち止まって冷静に判断することをおすすめします。
メリットばかりを強調し、リスクの説明をしない
- 不動産投資は、常にリスクと隣り合わせです。
空室、家賃下落、金利上昇、災害など、起こりうるリスクは多岐にわたります。誠実な会社であれば、これらのリスクをきちんと説明し、対策まで含めて提案してくれます。
しかし、節税効果や高い利回りといったメリットばかりを並べ立て、リスクの説明を怠ったり、質問してもはぐらかしたりする会社は信用できません。うまい話には裏があると考えましょう。
「絶対に儲かる」など断定的な表現を使う
- 投資の世界に「絶対」はありません。「絶対に儲かる」「100%損はしない」といった断定的な表現を使って勧誘してくる会社は、景品表示法に違反している可能性もあり、非常に危険です。
将来の家賃収入や物件価格を保証するような発言も同様です。不動産市況は常に変動するものであり、将来を確約することは誰にもできません。冷静で客観的なデータに基づいた説明をしてくれる会社を選びましょう。
電話やメールでの勧誘がしつこい
- 一度問い合わせをしたり、セミナーに参加したりしただけで、昼夜を問わず電話がかかってきたり、大量のメールが送られてきたりするような会社は要注意です。
こちらの都合を考えないしつこい勧誘は、顧客のペースを尊重しない会社の体質を表しています。断っているにもかかわらず勧誘がやまない場合は、きっぱりと関係を断つ勇気も必要です。
契約を急がせる・強引な営業をする
- 「この物件は人気ですぐになくなります」「今日中に決めないと他の人に取られますよ」など、冷静な判断をさせないように契約を急がせるのは、悪質な業者の常套手段です。
不動産は高額な買い物であり、熟慮する時間が必要です。こちらの疑問や不安が解消されないまま契約を迫ったり、長時間拘束してサインさせようとしたりするような強引な営業に は、絶対に応じてはいけません。
質問に曖昧な答えしかしない
- 物件の詳細や手数料、リスクについて具体的な質問をした際に、明確な答えが返ってこなかったり、「大丈夫です」「問題ありません」といった根拠のない返答しかしない担当者は信用できません。
納得できるまで丁寧に説明責任を果たしてくれる会社でなければ、安心して任せることはできません。
そもそも不動産投資とは?メリット・デメリットを解説
不動産投資とは、マンションやアパートなどの不動産を購入し、それを第三者に貸し出すことで家賃収入を得たり、購入時よりも高く売却して利益を得たりする資産運用方法です。株式や投資信託とは異なり、現物資産を持つという特徴があります。
ここでは、不動産投資を始める前に知っておくべき基本的なメリットとデメリットを、分かりやすく解説していきます。
不動産投資の7つのメリット
将来の安定や節税対策など、さまざまな目的で注目される7つのメリットを見ていきましょう。
少額の自己資金で大きな資産を築ける(レバレッジ効果)
不動産投資の大きなメリットは、金融機関からの融資を利用できる点です。これにより、自己資金が少なくても、それを「てこ(レバレッジ)」のように使って大きな金額の物件を購入できます。
例えば、自己資金300万円で3,000万円の物件を購入できれば、10倍のレバレッジをかけたことになります。このレバレッジ効果により、効率的に資産を拡大していくことが可能です。
長期にわたり安定した家賃収入(インカムゲイン)が期待できる
不動産投資の基本は、入居者から毎月得られる家賃収入(インカムゲイン)です。景気の変動による影響を受けにくく、一度入居者が決まれば、空室にならない限り安定した収入が長期にわたって続きます。
これは、価格変動が激しい金融商品にはない大きな魅力です。将来の私的年金として、また、給与以外の収入の柱として、生活に安定と安心をもたらしてくれます。
相続税対策になる
現金や預貯金を相続する場合、その金額がそのまま相続税の評価額となります。
しかし、不動産の場合は、実際の取引価格よりも低い「相続税評価額」で評価されるため、相続税を圧縮する効果が期待できます。
特に、賃貸用の不動産はさらに評価額が低くなるため、将来の相続を見据えている方にとって、有効な節税対策となりえます。
所得税・住民税の節税につながる場合がある
不動産投資で得た所得(不動産所得)は、給与所得など他の所得と合算して税金を計算します(損益通算)。
もし、減価償却費やローン金利などの経費が家賃収入を上回り、不動産所得が赤字になった場合、その赤字分を給与所得などから差し引くことができます。
その結果、課税所得が減り、所得税や住民税が還付・軽減される可能性があります。
団体信用生命保険で生命保険の代わりになる
不動産投資ローンを組む際には、通常「団体信用生命保険(団信)」への加入が義務付けられます。
これは、ローン契約者にもしものこと(死亡・高度障害)があった場合、保険金で残りのローンが完済される仕組みです。残された家族には、ローン返済の負担がない収益物件が資産として残ります。
これは、生命保険と同様の効果を持つと言えるでしょう。
インフレに強い現物資産である
インフレーション(インフレ)が起こると、物価が上昇し、現金の価値は相対的に目減りしてしまいます。
一方、不動産のような現物資産は、インフレに合わせてその価値や家賃が上昇する傾向があります。
そのため、不動産投資はインフレヘッジ、つまりインフレによる資産価値の減少を防ぐ有効な手段となります。
売却して利益(キャピタルゲイン)を狙うことも可能
不動産投資の利益は、家賃収入(インカムゲイン)だけではありません。購入した時よりも不動産価格が上昇したタイミングで売却し、売却益(キャピタルゲイン)を得ることも可能です。
景気の動向や都市開発計画などを読み、適切なタイミングで売却することで、大きな利益を得るチャンスもあります。
不動産投資のデメリット(リスク)と対策
不動産投資には多くのメリットがある一方で、無視できないデメリットやリスクも存在します。これらのリスクを事前に理解し、適切な対策を講じることが、長期的に成功するための鍵となります。
ここでは代表的なリスクとその対策について解説します。
空室リスク
購入した物件に入居者が決まらず、家賃収入が得られない状態が「空室リスク」です。
家賃収入がなければ、ローンの返済や管理費は自己資金から支出しなければなりません。
- 駅から近い、周辺環境がよいなど、賃貸需要の高いエリアの物件を選ぶ。入居者募集能力の高い、信頼できる管理会社に委託する。
家賃滞納リスク
入居者が家賃を支払ってくれないのが「家賃滞納リスク」です。家賃が滞納されると収入が途絶えるだけでなく、督促や法的手続きに手間と費用がかかる場合もあります。
- 入居審査を厳格に行う管理会社を選ぶ。
- 滞納保証がついたプランや家賃保証会社を利用する。
老朽化・修繕リスク
建物は経年劣化により、修繕が必要になります。給湯器の故障や外壁の補修、リフォームなど、突発的な出費や計画的な大規模修繕が発生するリスクです。
- 将来の修繕に備え、毎月一定額を修繕積立金として計画的に積み立てておく。
- 購入前に物件の修繕履歴や長期修繕計画を確認する。
価格変動・売却損リスク
景気の悪化や周辺環境の変化などにより、不動産の価値が下落し、購入時よりも低い価格でしか売却できなくなるリスクです。
- 短期的な価格変動に惑わされず、長期的な視点で資産価値が維持されやすい物件を選ぶ。
- 購入時に売却時のこと(出口戦略)まで考えておく。
金利上昇リスク
不動産投資ローンの多くは変動金利です。将来、市場金利が上昇すると、それに伴いローン金利も上がり、毎月の返済額が増加するリスクがあります。
- 金利が上昇してもキャッシュフローが悪化しないよう、余裕を持った資金計画を立てる。
- 金利の低い時期に固定金利を選択する、繰り上げ返済を検討する。
流動性の低さ(すぐに現金化できないリスク)
不動産は株式などと違い、売却しようと思ってもすぐに買い手が見つかるとは限りません。現金が必要になった時に、すぐに現金化できない「流動性の低さ」もリスクのひとつです。
- 生活防衛資金など、ある程度の現金は手元に残しておく。
- 売りやすい(需要の高い)物件を選ぶことを心がける。
災害リスク
地震や台風、水害などの自然災害によって、建物が損傷したり倒壊したりするリスクです。火災保険や地震保険で備えることはできますが、被害のすべてをカバーできるとは限りません。
- ハザードマップなどを確認し、災害リスクの低いエリアを選ぶ。
- 火災保険や地震保険に適切に加入する。新耐震基準を満たした物件を選ぶ。
事故リスク
物件の室内で、自殺や孤独死、事件などが発生するリスクです。いわゆる「事故物件」になると、資産価値や家賃が大幅に下落する可能性があります。
- 単身の高齢者が入居する場合は、見守りサービスなどを検討する。
- 事故が起きた際の原状回復費用や家賃下落分を補償する保険に加入する。
【5ステップで解説】不動産投資の始め方
ここでは、不動産投資を始めるための具体的な5つのステップを解説します。
STEP1|自己資金計画・リスク許容度の棚卸し
まず初めに行うのは、自分自身の状況を把握することです。不動産投資にどれくらいの自己資金を投入できるのか、毎月の収支はどうか、などを明確にします。
また、どの程度のリスクなら受け入れられるか(リスク許容度)を考えることも重要です。
この最初のステップで自分の立ち位置をしっかり確認することが、無理のない投資計画を立てるための土台となります。
STEP2|不動産投資会社に相談・面談
次に、信頼できる不動産投資会社を探し、専門家に相談します。複数の会社と面談し、それぞれの会社の特徴や提案内容を比較検討しましょう。
この段階で、自分の投資目的や資金計画を正直に伝え、親身になって相談に乗ってくれるパートナーを見つけることが成功の鍵です。
無料セミナーや個別相談会などを活用するのもよいでしょう。
STEP3|物件の提案・検討
不動産投資会社との面談を経て、あなたの希望や条件に合った物件の提案を受けます。
提案された物件については、立地や築年数、利回りなどの表面的な情報だけでなく、将来性や想定されるリスクも含めて深く検討します。
可能であれば、実際に現地に足を運び、自分の目で周辺環境や建物の状態を確認することが大切です。
STEP4|不動産売買契約・ローン契約
購入したい物件が決まったら、不動産売買契約を結びます。契約前には「重要事項説明」を宅地建物取引士から受け、内容を十分に理解した上で署名・捺印しましょう。
同時に、金融機関にローンの申し込みを行い、融資契約(金銭消費貸借契約)を締結します。
多くの手続きが必要になるため、不動産会社の担当者と密に連携を取りながら進めます。
STEP5|物件の引き渡し・賃貸管理開始
ローンの融資が実行され、売主への代金の支払いが完了すると、物件の鍵が引き渡され、晴れて物件の所有者となります。ここからが、いよいよオーナーとしてのスタートです。
引き渡し後は、速やかに入居者募集を開始し、賃貸経営を始めます。管理業務を不動産会社に委託する場合は、管理委託契約を結び、家賃収入を得るための運用を本格化させていきます。
不動産投資の費用は?自己資金はいくら必要?
不動産投資を始めるにあたって、最も気になることの一つが「費用」の問題でしょう。
「自己資金は一体いくら準備すればいいのか」「物件価格以外にどんな費用がかかるのか」といった疑問にお答えします。
事前に必要な資金を把握し、余裕を持った計画を立てることが、安心して投資を始めるための第一歩です。
不動産投資に必要な自己資金の目安は物件価格の1〜2割
一般的に、不動産投資を始める際に必要となる自己資金の目安は、購入する物件価格の10%〜20%程度と言われています。
これは、ローンの頭金や後述する諸費用に充てるための資金です。例えば、2,000万円の物件を購入する場合、200万円〜400万円程度の自己資金があると安心です。
もちろん、金融機関や個人の属性によっては、より少ない自己資金で始められるケースもあります。
自己資金以外にかかる諸費用の内訳
物件価格とは別に、購入時にはさまざまな「諸費用」が発生します。この諸費用は、物件価格の7%〜10%程度が目安とされています。現金で支払う必要があるため、自己資金計画には必ず含めておきましょう。
- 仲介手数料:不動産会社に支払う手数料
- 印紙税:売買契約書やローン契約書に貼る印紙代
- 登録免許税:不動産の所有権を登記するための税金
- 不動産取得税:不動産を取得した際に課される税金(購入後にかかります)
- 司法書士報酬:登記手続きを代行する司法書士への報酬
- ローン事務手数料・保証料:金融機関に支払う手数料
- 火災保険料・地震保険料
【出口戦略を考えよう】不動産投資の3つのゴール
不動産投資は、物件を購入して家賃収入を得るだけでなく、最終的にその物件をどうするのかという「出口戦略」まで考えておくことが非常に重要です。
購入する段階で出口を意識しておくことで、投資全体の成功確率を大きく高めることができます。不動産投資の主なゴール(出口戦略)には、以下の3つがあります。
| 出口戦略 | 目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 売却 | 売却益(キャピタルゲイン)の獲得 | ・不動産価格が上昇したタイミングで売却し、利益を狙う ・将来の値上がりが期待できるエリアの物件で重要 |
| 長期保有 | 安定収入(インカムゲイン)の確保 | ・ローン完済後、家賃収入が不労所得になる ・私的年金や相続資産として活用 |
| 借換 | 投資効率の改善 | ・より低金利のローンに乗り換え、キャッシュフローを改善 ・投資途中の経営状況を好転させるための戦略(※厳密には最終ゴールではない) |
不動産投資に関するよくある質問
ここでは、初心者の方から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
「不動産投資はやめとけ」という声の真相から、サラリーマンや公務員の副業としての可能性まで、気になるポイントを解消していきます。
「不動産投資はやめとけ」と言われる理由は?
- 「不動産投資はやめとけ」と言われる主な理由は、リスクを十分に理解せずに始めたり、悪質な業者に騙されたりして失敗した人の話が広まっているためです。
空室リスクや金利上昇リスクなど、不動産投資には確かにリスクが存在します。
しかし、これらのリスクを正しく理解し、信頼できるパートナーと組んで適切な対策を講じれば、過度に恐れる必要はありません。
不動産投資で元を取るまで何年かかる?
- 投資した自己資金を回収できるまでの期間は、物件の価格や利回り、ローンの条件などによって大きく異なります。
一般的には、キャッシュフロー(家賃収入から経費やローン返済を引いた手残り)を積み上げていく形になります。
一概には言えませんが、シミュレーション上は10年〜20年程度で回収できるケースが多いようです。繰り上げ返済などを活用すれば、期間を短縮することも可能です。
不動産投資は儲かる?
- 「儲かる」の定義にもよりますが、不動産投資は短期間で大きな利益を得るハイリスク・ハイリターンな投資ではありません。
むしろ、長期的な視点で、安定した家賃収入を着実に積み上げていくミドルリスク・ミドルリターンの資産形成手法です。
正しい知識と戦略をもって臨めば、給与以外の収入の柱をつくり、将来の資産を築いていくことは十分に可能です。
サラリーマンの副業として、不動産投資はできる?
- はい、可能です。むしろ、安定した給与収入があるサラリーマンは、金融機関からの融資審査で有利になるため、不動産投資に向いていると言えます。
物件の管理業務を信頼できる管理会社に委託すれば、本業に支障をきたすことなくオーナー業を続けられます。
実際に、不動産投資を行っている人の多くは、本業を持つサラリーマンです。
不動産投資を始めるのに年収はいくらが目安?
- 金融機関が融資を判断する際、年収は重要な要素の一つです。一般的には、年収500万円以上が一つの目安とされていますが、これはあくまで目安です。
勤務先の規模や勤続年数、自己資金の額など、個人の属性によって総合的に判断されます。
年収が500万円未満でも、融資を受けられるケースもありますので、まずは不動産会社に相談してみることをおすすめします。
公務員でも不動産投資できる?
- 公務員も不動産投資を行うことは可能です。ただし、国家公務員法や地方公務員法で定められている副業規定に注意が必要です。
一般的に、事業的規模と見なされない範囲、具体的には「5棟10室未満」の規模であれば、資産運用の一環として認められるケースがほとんどです。事前に所属する団体の服務規程を確認しておくと、より安心です。
不動産投資の利回りは何%以上が理想?
- 理想的な利回りは、物件のエリアや種別(新築か中古か、都心か地方かなど)によって大きく異なります。
一般的に、リスクの低い都心の新築・築浅物件は利回りが低く(表面利回り3〜5%程度)、リスクの高い地方の中古物件は利回りが高くなる傾向があります。
大切なのは、利回りの高さだけで判断せず、空室リスクや修繕費なども考慮した実質利回りで収支をシミュレーションすることです。
不動産投資の融資額は年収の何倍ですか?
- 融資額の目安は、一般的に年収の7倍〜10倍程度と言われることが多いですが、これも金融機関の方針や個人の属性、物件の収益性などによって大きく変動します。
複数の物件を所有している場合や、他の借り入れがある場合などは、融資額が少なくなることもあります。まずは自身の年収や資産状況から、どれくらいの融資が受けられそうか、不動産会社を通じて金融機関に打診してみるのがよいでしょう。
「サラリーマンは不動産投資でカモにされる」は本当?
- 残念ながら、知識の少ないサラリーマンをターゲットにした悪質な業者がいることは事実です。
しかし、これはサラリーマンに限った話ではありません。不動産投資の知識を身につけ、信頼できる会社を慎重に選ぶことで、「カモにされる」リスクは大幅に減らすことができます。
うまい話にはすぐに飛びつかず、この記事で紹介したような会社選びのポイントをしっかり押さえることが大切です。
初心者がまず読むべき必読書3選
不動産投資で成功するためには、継続的な情報収集と学習が欠かせません。インターネットやセミナーも有用ですが、体系的に知識を深めるには、書籍を読むのがおすすめです。
初心者向けに図解を多用した分かりやすい入門書から、経験者のリアルな失敗談をまとめた本、税金や法律について掘り下げた専門書まで、さまざまな種類の本が出版されています。まずは自分のレベルや知りたいことに合わせて、数冊手に取ってみてはいかがでしょうか。
まとめ
この記事では、不動産投資会社の選び方から、不動産投資のメリット・デメリット、具体的な始め方までを網羅的に解説しました。不動産投資は、将来の資産形成や安定収入の確保に有効な手段ですが、成功のためには正しい知識と信頼できるパートナーが不可欠です。
特に、長期にわたるパートナーとなる不動産投資会社選びは、最も重要なポイントと言えるでしょう。今回ご紹介した7つの選び方を参考に、複数の会社を比較検討し、ご自身の投資目標に最も合った一社を見つけてください。
まずは無料相談などを活用して、専門家の話を聞くことから第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
記事をシェアする
あなたにおすすめの記事
アンケートサイトのおすすめ人気ランキング10選!アンケートモニターは副業で稼げる?
貯蓄型保険のおすすめ人気ランキング18選【一括払い・一時払い】女性向けや10年満期シミュレーション
ネット銀行のおすすめ人気ランキング14選!やめた方がいい?学生や初心者向けのサービスも厳選
ポイ活は危険でリスクあり?安全に稼ぐための注意点を徹底解説
歩くだけポイントを稼げるポイ活アプリのおすすめランキング15選
「楽天市場」はどのポイントサイトを経由するのが一番お得?おすすめの稼ぐコツを紹介
「Amazon」はどのポイントサイトを経由するのが一番お得?おすすめの稼ぐコツを紹介
ポイ活におすすめの人気ポイントサイト・アプリ比較ランキング23選【ユーザー投票】
新着の記事
市販の妊娠線予防クリームおすすめ8選!後悔しないための選び方と効果的な塗り方
ピンクカラーシャンプーのおすすめ9選!髪色長持ちの選び方とコツ
【2026年最新】リファのヘアアイロンはどれがいい?全種比較と失敗しない選び方
キャンプ用扇風機おすすめランキング15選!最強の暑さ対策&冬の空気循環まで
【ハミングウォーターの口コミ】デメリットや評判をAmebaブログから徹底検証
解約金なしウォーターサーバーってある?|契約期間の縛りがない機種を紹介
リファのドライヤーはどれがいい?全5種比較!効果や使い方も解説
飲むヨーグルトのおすすめ14選!太ると言われる原因や効果を解説
リファのシャワーヘッドで肌と髪はどう変わった?実際の口コミから見えた効果の真実
しずくりあ全3モデルを徹底比較!月額2,640円で変わる「ボトルのない暮らし」の魅力
すべてのカテゴリ
参考価格の表記について
当サイトでは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングの中から、同一商品の価格を比較し、そのうち最も値段の安いものを「参考価格」と定義しております。
また、商品価格(税表記の有無・送料等も含む)は常に変動しており、当サイトへの反映が一部遅延する場合がございますので、最終的な購入価格はリンク先の各ページで改めてご確認いただきますようよろしくお願い申し上げます。
※当サイト内にて[PR][Sponsored]の表記がある商品はアフィリエイトプログラムにより広告収益を得て運用を行っております。




























