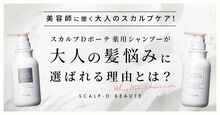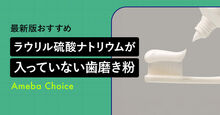「アイライナーって種類が多くて、どれを選べばいいか分からない…」「引いてもすぐに滲んでパンダ目になっちゃう」「自分の目の形に合う引き方が知りたい!」そんなお悩みはありませんか?アイライナーは、目元の印象を大きく左右する重要なアイテムですが、選び方や使い方が難しいと感じる方も多いかもしれません。
この記事では、アイライナーの種類や選び方の基本から、最新のおすすめ商品、さらには目の形別のお悩み解消テクニックまで、徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたにぴったりの運命の1本が見つかり、毎日のメイクがもっと楽しくなるはずです!
- 失敗しないアイライナーの選び方|5つの重要ポイント
- 1. 種類で選ぶ|リキッド、ペンシル、ジェル…
- 2. 仕上がりで選ぶ|ナチュラルorくっきり?なりたい印象で選ぶ
- 3. 機能性で選ぶ|落ちにくさ、描きやすさ、肌への優しさもチェック
- 4. カラーで選ぶ|定番カラーからトレンドカラーまで、印象を操る
- 5. 価格帯で選ぶ|プチプラ?デパコス?予算に合わせた賢い選び方
- 【最新版】タイプ別おすすめアイライナー11選
- リキッドアイライナーのおすすめ7選
- ペンシルアイライナーのおすすめ4選
- 【目の形別】アイラインの引き方講座
- 一重さん向け|すっきりデカ目に見せるアイラインの引き方
- 奥二重さん向け|自然なのに印象的な目元を作るアイラインの引き方
- 二重さん向け|魅力を最大限に引き出すアイラインの引き方
- 【FAQ】アイライナーに関するよくある質問
- まとめ
失敗しないアイライナーの選び方|5つの重要ポイント
アイライナー選びで失敗しないためには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。ここでは、最適な1本を見つけるための5つの重要な選び方を解説します。これらのポイントを参考に、自分にぴったりのアイライナーを見つけてみてください。
1. 種類で選ぶ|リキッド、ペンシル、ジェル…

アイライナーには主に「リキッド」「ペンシル」「ジェル」の3つのタイプがあり、それぞれ特徴が異なります。ここでは、それぞれのタイプの特徴を見ていきましょう。
リキッドアイライナー
リキッドアイライナーは液体タイプで、筆やフェルトペンを使ってラインを描きます。細い線から太い線まで、くっきりとしたシャープなラインを描くのが得意で、発色がよくツヤのある仕上がりになるものが多いのが特徴です。
メリットとしては、落ちにくく滲みにくい製品が多い点(特にフィルムタイプやウォータープルーフ)が挙げられ、目力を強調したい方におすすめです。
一方で、筆先がしなるため、慣れるまでは手元がぶれやすく修正がやや難しいというデメリットも。初心者さんには少し練習が必要かもしれません。
くっきりとしたラインで目力をアップさせたい人、アイラインを長時間キープしたい人、メイクに慣れている人に適したタイプといえるでしょう。
ペンシルアイライナー
ペンシルアイライナーには鉛筆タイプと繰り出しタイプがあり、芯が柔らかく、なめらかな描き心地が特徴です。
仕上がりはふんわりとした自然な印象になります。ラインを引いた後に指や綿棒でぼかせば、アイシャドウのような使い方も可能です。
描きやすく、失敗しても修正しやすいため、初心者さんにおすすめで、ナチュラルメイクにもぴったり。
ただし、リキッドに比べて油分に弱い傾向があり、商品によってはやや落ちやすく滲みやすいこともデメリットとして考えられます。アイライン初心者さん、ナチュラルメイクが好きな人におすすめです。
ジェルアイライナー
ジェルアイライナーは、なめらかなジェル状のテクスチャーで、ペンシル型と、ブラシにとって使うジャータイプの2種類があります。
発色がよく、くっきりとしたラインも、ぼかしたアンニュイなラインも描けるのが魅力です。リキッドのような発色の良さと、ペンシルのような描きやすさを兼ね備えていると言えるでしょう。密着度が高く、落ちにくいものが多いのもメリットです
ただし、ジャータイプは別途ブラシが必要な場合があり、持ち運びには少し不便かもしれません。ペンシル型なら手軽に使えます。発色も落ちにくさも重視したい人や、様々なライン表現を楽しみたい人におすすめです。
2. 仕上がりで選ぶ|ナチュラルorくっきり?なりたい印象で選ぶ

アイライナーは、その質感によっても仕上がりの印象が大きく変わります。「マット」「ツヤ」「ラメ」といった質感の違いを知り、なりたいイメージに合わせて選ぶのも楽しいでしょう。
マットな仕上がり
マットな仕上がりは、光沢のない落ち着いた質感が特徴です。上品で知的な印象を与え、どんなシーンにもなじみやすいため、普段使いやオフィスメイクにも最適といえます。
ツヤのある仕上がり
ツヤのある仕上がりは、程よい光沢感があり、目元をぱっと明るく、華やかに見せてくれます。目を大きく見せる効果も期待できるため、パーティーシーンなど特別な日にもぴったりです。
ラメ・パール感のある仕上がり
ラメやパール感のある仕上がりは、きらめきが目元にアクセントを加え、印象的で個性的な雰囲気を演出します。イベントや気分を変えたい時におすすめの質感です。
3. 機能性で選ぶ|落ちにくさ、描きやすさ、肌への優しさもチェック
アイライナーを選ぶ際は、仕上がりだけでなく機能性も重要なポイントです。自分のライフスタイルや肌質に合わせて、必要な機能をチェックしましょう。
落ちにくさ(ウォータープルーフ/スマッジプルーフ)
落ちにくさに関する機能としては、「ウォータープルーフ」と「スマッジプルーフ」があります。
ウォータープルーフは汗や水、涙に強いタイプで、夏のレジャーやスポーツシーンでも安心。「パンダ目」を防ぎたい方には必須の機能です。
一方、スマッジプルーフは皮脂や摩擦に強いタイプ。まばたきなどでラインが擦れて滲んでしまうのを防ぐため、オイリー肌の方や、アイメイクが崩れやすい方におすすめです。
お湯でオフ
お湯でオフできるタイプは、専用のクレンジングを使わなくても簡単に落とせるのがメリットです。メイクオフの手間が省け、目元への負担も軽減できるでしょう。まつ毛エクステをしている方にも人気があります。
速乾性
速乾性のあるアイライナーは、ラインを引いてすぐに乾くため、まぶたにラインが転写されたり、よれたりするのを防いでくれます。忙しい朝にも便利な機能です。
肌への優しさ(低刺激性)
肌への優しさを重視するなら、低刺激性の製品を選びましょう。染料不使用、美容成分配合、アレルギーテスト済みなど、目元の皮膚に配慮した製品もあります。
敏感肌の方や、目元の乾燥が気になる方は、成分表示もチェックしてみるとよいでしょう。
4. カラーで選ぶ|定番カラーからトレンドカラーまで、印象を操る

アイライナーの色を変えるだけで、目元の印象は大きく変わります。定番カラーからトレンドカラーまで、様々な色を楽しみましょう。
ブラック
ブラックは、目元をくっきりと引き締め、最も目力を強調できる定番カラーです。フォーマルな場面にも適しており、一本持っておくと重宝します。
ブラウン(ダークブラウン、ライトブラウンなど)
ブラウン系のカラーは、ブラックよりも柔らかい印象で、ナチュラルに仕上がります。
抜け感を出したい時や、優しい雰囲気に見せたい時におすすめ。髪色や瞳の色に合わせて、ダークブラウンやライトブラウンなど、色味を選ぶのもよいでしょう。
グレー
グレーは、ブラックほど強くなく、ブラウンよりもクールな印象を与えます。知的で洗練された雰囲気を演出したいときにぴったりのカラーです。
ニュアンスカラー(カーキ、バーガンディ、ネイビー、グレージュなど)
近年人気のニュアンスカラーは、さりげなく個性を演出し、おしゃれな印象を与えます。
例えば、カーキは肌なじみがよくこなれ感を演出し、バーガンディは血色感をプラスして色っぽく女性らしい印象に。ネイビーは白目をきれいに見せ透明感をアップさせ、グレージュは柔らかさとクールさを両立した絶妙なカラーとして人気です。
5. 価格帯で選ぶ|プチプラ?デパコス?予算に合わせた賢い選び方
アイライナーは、ドラッグストアなどで手軽に購入できる「プチプラ」から、百貨店などで扱われる「デパコス」まで、幅広い価格帯の商品があります。それぞれの特徴を知り、予算に合わせて選びましょう。
プチプラ(〜1,500円程度)
プチプラアイライナーの最大のメリットは、なんといっても手頃な価格です。トレンドカラーや新しいタイプを気軽に試すことができますし、種類も豊富で、「キャンメイク」や「セザンヌ」など定番人気の優秀なアイテムがたくさんあります。
ただし、商品によっては色持ちや発色がデパコスに比べてやや劣る場合もあり、パッケージがシンプルなものが多い傾向があります。
デパコス(3,000円〜)
デパコスのアイライナーは、高品質な原料や処方にこだわった製品が多く、発色、色持ち、描きやすさなどの機能性に優れている傾向があります。
洗練されたパッケージデザインも魅力で、「シャネル」や「ディオール」など、持っているだけで気分が上がるブランドも多いです。一方で、価格が高めなので、気軽に試すのは難しいかもしれません。
【最新版】タイプ別おすすめアイライナー11選
ここからは、Amebaチョイス編集部が独自に厳選した、おすすめのアイライナーをタイプ別にご紹介します。ぜひ自分にぴったりなアイライナーを探してみてくださいね。
リキッドアイライナーのおすすめ7選
ペンシルアイライナーのおすすめ4選
【目の形別】アイラインの引き方講座
アイライナーは、ただ引けばいいというものではありません。自分の目の形に合わせて引き方を変えることで、より魅力的で印象的な目元をつくることができます。
ここでは、一重さん、奥二重さん、二重さん、それぞれの目の形に合ったアイラインの引き方のコツを解説します。
一重さん向け|すっきりデカ目に見せるアイラインの引き方
一重さんは、まぶたがアイラインにかぶさって隠れてしまったり、ラインを太くしすぎるとかえって目が小さく見えたり、きつい印象になったりすることがあります。以下のポイントを押さえて、すっきりとしたデカ目を目指しましょう。
ポイント1: まつ毛のキワを丁寧に埋める
まずは、まつ毛とまつ毛の間を点で埋めるように、インラインを丁寧に引くことから始めましょう。これにより、自然に目のフレームが強調され、目力がアップします。
ポイント2: 目を開けた状態でラインの太さを確認
次に、目を開けた時に、ラインがまぶたに隠れず、ほんの少し見えるくらいの太さを確認することが大切です。細めに引いてから、少しずつ太さを調整していくのが失敗しないコツです。
ポイント3: 目尻は少し長めに
ポイント4: リキッドライナーがおすすめ目尻のラインは、実際の目の横幅よりも少し長めに引くのがおすすめです。これにより、目の横幅が強調されて大きく見せる効果があります。跳ね上げすぎず、目のカーブに沿って自然に流すのがポイントです。
ポイント4: リキッドライナーがおすすめ
一重さんには、細く、くっきりとしたラインが描きやすいリキッドライナーが特におすすめです。落ちにくいタイプを選べば、まぶたで擦れてもラインが消えにくく安心です。
奥二重さん向け|自然なのに印象的な目元を作るアイラインの引き方
奥二重さんは、目頭側の二重幅が狭く、アイラインが隠れてしまいがち。また、ラインを太く引くと二重幅が潰れて見えてしまうことも。自然でありながら印象的な目元をつくるためのポイントはこちらです。
ポイント1: 目尻側を重点的に
アイラインは目頭から全て引くのではなく、黒目の外側あたりから目尻にかけて引くのがおすすめです。特に目尻側を少し太めにすると、目の形とのバランスがよくなります。
ポイント2: 二重幅を潰さない細さで
目を開けたときに、ラインが二重幅に隠れてしまわない程度の細さを意識することが重要です。特に目頭側は細く引くか、もしくは引かない方がすっきりとした印象になります。
ポイント3: 目尻ラインで印象チェンジ
目尻のラインの角度で印象を変えることができます。少し跳ね上げるとクールな印象に、目のカーブに沿って下げ気味に描くと優しい印象になります。なりたいイメージに合わせて調整しましょう。
ポイント4: 滲みにくいタイプを選ぶ
奥二重さんは、二重のライン部分でアイラインが滲みやすい場合があります。そのため、ウォータープルーフやスマッジプルーフといった滲みにくいタイプのアイライナーを選ぶと安心です。
二重さん向け|魅力を最大限に引き出すアイラインの引き方
二重さんは、比較的どんなアイラインも似合いやすいですが、引き方次第でさらに魅力を引き出すことができます。基本的な引き方と、より垢抜ける応用テクニックをご紹介します。
基本の引き方
まず基本となるのは、まつ毛の生え際に沿って、細くラインを引くことです。目頭から目尻まで、できるだけ均一な太さで引くのがきれいに見せるポイントです。
応用テクニック
基本の引き方に慣れたら、応用テクニックにも挑戦してみましょう。例えば、目尻のラインを少し長めに引いたり、軽く跳ね上げたりするだけで印象を変えられます。その日の気分やファッションに合わせて楽しむのがおすすめです。
また、二重幅がしっかり見える二重さんは、カラーライナーがよく映えます。目尻だけポイントで入れたり、アイシャドウの色と合わせたりするのもおしゃれです。
さらに、あえてまつ毛のキワだけにインラインを引き、アイシャドウでグラデーションをつくると、抜け感のある洗練された目元になります。
【FAQ】アイライナーに関するよくある質問
アイライナーがすぐに滲んでしまいます。どうすればいいですか?
- アイライナーが滲んでしまう場合、いくつかの対策が考えられます。
まず、アイラインを引く前に、ティッシュやまぶた用の下地などでまぶたの油分を軽く押さえましょう。フェイスパウダーを薄くつけるのも効果的です。
また、アイシャドウベースを使うと、アイメイク全体の密着が高まり、ヨレや滲みを防ぐ効果が期待できます。もちろん、汗や皮脂に強いウォータープルーフやスマッジプルーフ処方のアイライナーを選ぶことも重要です。
さらに、引いたラインの上に、同系色のアイシャドウパウダーや透明なパウダーを軽く重ねると、密着度が高まり、滲みにくくなりますよ。
アイライナーをきれいに引くコツはありますか?
- アイライナーをきれいに引くためには、いくつかのコツがあります。まず、机などに肘をついて手元を固定すると、ブレにくくなります。
鏡を顔の下に置き、少し顎を引いて伏し目がちにすると、まぶたのキワが見やすくなり、ラインを引きやすくなります。
一気に引こうとせず、短い線を少しずつ繋げるように描くのも、ガタつきを防ぐポイントです。また、人によっては目尻から目の中央に向かって引く方が、自然なカーブを描きやすい場合もあります。ぜひご自身に合ったやり方を見つけてみてください。
アイライナーはどのくらいの期間で使い切るのが目安ですか?
- アイライナーの使用期限は、商品の種類や使用頻度によって異なりますが、一般的には開封後半年から1年程度が目安とされています。
特にリキッドタイプは容器内で雑菌が繁殖しやすい可能性があるため、注意が必要です。インクが出にくくなったり、かすれたり、ペンシルが硬くなったり、以前と違う匂いがするなど、変化を感じたら、使用期限内であっても安全のために買い替えを検討しましょう。
ペンシルアイライナーの芯が硬くて描きにくいです。どうすればいいですか?
- ペンシルアイライナーの芯が硬くて描きにくい場合、いくつか試せる方法があります。まず、手の甲などで数回線を描いて、芯の表面を柔らかくしてから使うと描きやすくなることがあります。
また、芯を少し温めるのも効果的です。ドライヤーの温風をごく短時間当てたり、清潔な指で軽く温めたりすると、芯が柔らかくなり描きやすくなります(ただし、火傷には十分注意し、自己責任で行ってください)。
鉛筆タイプのペンシルアイライナーは、専用のシャープナーで定期的に削ることで、常に描きやすい状態を保つことができます。
カラーアイライナーを使いこなすにはどうすればいいですか?
- カラーアイライナーは難しそうに見えるかもしれませんが、意外と簡単に取り入れられます。まずは、目尻だけに細くポイントとして入れるところから始めてみてはいかがでしょうか。さりげないアクセントになります。
アイシャドウと同系色のカラーライナーを選ぶと、メイク全体にまとまりが出て自然になじみます。下まぶたのキワ(黒目の下や目尻のみ)に入れると、抜け感のあるおしゃれな印象になります。また、いつものブラックやブラウンのラインの上に、細く重ねてみるのもおすすめです。
まとめ
この記事では、アイライナー選びで失敗しないための5つのポイント、タイプ別のおすすめ商品、そして目の形に合わせたアイラインの引き方まで、詳しく解説してきました。
もう一度、選び方のポイントをおさらいしましょう。
- 種類で選ぶ: リキッド、ペンシル、ジェルの特徴を知り、スキルや仕上がりに合わせる。
- 仕上がりで選ぶ: マット、ツヤ、ラメからなりたい印象で選ぶ。
- 機能性で選ぶ: 落ちにくさ、描きやすさ、お湯オフ、肌への優しさなどをチェック。
- カラーで選ぶ: 定番色からトレンドカラーまで、印象を操る色を選ぶ。
- 価格帯で選ぶ: プチプラとデパコスの特徴を知り、予算に合わせて賢く選ぶ。
これらのポイントを参考に、ぜひご自身にぴったりのアイライナーを見つけてください。タイプ別のおすすめアイライナー紹介 や、目の形別の引き方講座 も、きっとあなたのアイライナー選びの助けになるはずです。
さあ、あなたも自分にぴったりのアイライナーを手に入れて、毎日のメイクをもっと楽しみ、さらに魅力的な自分を発見してみませんか?
記事をシェアする
あなたにおすすめの記事
リファのシャワーヘッドで肌と髪はどう変わった?実際の口コミから見えた効果の真実
30代女性のボリューム悩みに!スカルプDボーテ薬用シャンプーで始める頭皮ケア【美容師監修】
ラウリル硫酸ナトリウム不使用の歯磨き粉おすすめ7選!口内炎や危険性も解説
スキンヘッド用シェーバーのおすすめ14選!深剃りと時短で快適に
フェイススチーマーのおすすめ人気ランキング15選!効果的な使い方も紹介【安い・コスパ最強】
【2026年版】まとめ髪ワックスおすすめ15選!アホ毛・崩れ防止の選び方&付け方を美容師が解説
【2026年最新】スタイリングオイルのおすすめ10選!髪質に合わせた選び方を紹介
市販の痛み止め(鎮痛剤)のおすすめ人気ランキング13選【歯痛、生理痛、頭痛】
業務用脱毛器おすすめランキング7選|失敗しない選び方と「利益が出る」マシンの条件
かすみ目に効く目薬のおすすめ人気ランキング15選!コンタクト対応・老眼による目のかすみに
新着の記事
【口コミ】Anker Soundcore Liberty 4の評判をAmebaブログから徹底検証!
Wiiソフトのおすすめ名作選!人気の神ゲーや未移植の作品を紹介
ワクワクメールの口コミと評判!知恵袋・男女の本音・業者・アプリ通話実態
ハッピーメールの口コミと評判|知恵袋の「やめとけ」理由・値段・危険人物を解説
マキタの掃除機おすすめ9選!最強コードレスの選び方ガイド
ダイソン掃除機どれがいい?人気おすすめ比較ランキングと後悔しない選び方
市販の妊娠線予防クリームおすすめ8選!後悔しないための選び方と効果的な塗り方
ピンクカラーシャンプーのおすすめ9選!髪色長持ちの選び方とコツ
【2026年最新】リファのヘアアイロンはどれがいい?全種比較と失敗しない選び方
キャンプ用扇風機おすすめランキング15選!最強の暑さ対策&冬の空気循環まで
すべてのカテゴリ
参考価格の表記について
当サイトでは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングの中から、同一商品の価格を比較し、そのうち最も値段の安いものを「参考価格」と定義しております。
また、商品価格(税表記の有無・送料等も含む)は常に変動しており、当サイトへの反映が一部遅延する場合がございますので、最終的な購入価格はリンク先の各ページで改めてご確認いただきますようよろしくお願い申し上げます。
※当サイト内にて[PR][Sponsored]の表記がある商品はアフィリエイトプログラムにより広告収益を得て運用を行っております。